会長挨拶 |
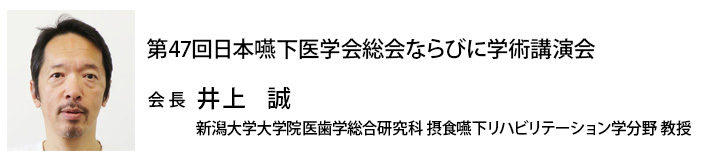 |
| このたび、令和6年2月9日(金)、10日(土)の両日、新潟市芸術文化会館において第47回日本嚥下医学会総会ならびに学術講演会を開催させていただくことになりました。伝統ある本学会を歯科医として担当させていただくことになり、大変名誉なことであると同時に、非常に身の引き締まる思いでいます。改めまして理事長の梅崎俊郎先生、理事会、評議員会、会員の皆様方に心から感謝申し上げます。 今回の学会のテーマは「サイエンス」を磨き「食べる」を支える、としています。超高齢社会となって久しい日本では、高齢者の主たる死亡原因である肺炎の多くが誤嚥性であり、その原因が摂食嚥下障害であることは周知のものとなりつつあります。しかし加齢や種々の基礎疾患に伴って多様化する摂食嚥下障害への対応は難しく、多くが食事形態の変更であったり、姿勢調整などの対症療法に限られています。一方で、食べる基盤を形成している私たちの体のしくみはまだまだ分からないことばかりといっても過言ではありません。嚥下運動ひとつとっても、嚥下反射にかかわる末梢感覚の受容機構、反射弓を形成する脳幹の神経ネットワーク、随意嚥下を可能とさせている上位脳の構成、嚥下筋の構成・活動パターン・実際の嚥下運動への関与など、いまだブラックボックスばかりです。嚥下運動を機能的に理解しようという試みについては、古典的な筋電図や神経記録、また嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査に加えて、高解像度マノメトリやCTなどが加わることで広がりをみせてはいるものの、いずれも研究の範疇を超えていません。今回の学術講演会では、基調講演、教育講演、シンポジウム、パネルディスカッションなど、これまでの構成の流れを踏襲しつつ、将来の臨床へのヒントとなるような基礎研究や機能研究をベースとした企画を準備しています。さらに昨今の臨床ニーズを踏まえて、多職種連携、遠隔医療、歯科臨床からの発信などといった独自の企画も考えています。また、本学会の特色のひとつである耳鼻咽頭科領域の教育セミナーに関しては、京都府立医科大学の杉山庸一郎先生にもご協力いただく予定にしています。 ポストコングレスセミナーは2月10日、本学会終了直後に2本立てて行う予定です。解剖生理から口腔ケア、嚥下評価、訓練といった高齢者の摂食嚥下障害に携わる皆様に明日からのヒントなるような内容を用意して、各分野の専門家の先生方に最新の知見を含めてご講義いただく予定です。 プログラム完成は夏前を予定しており、準備ができ次第皆様に披露する予定で、現在鋭意準備中です。ご参加の先生方のご期待に少しでも添えるように教室員一丸となって頑張ります。何卒盛大なるご支援をお願い申し上げますとともに、たくさんの先生方のご来場をお待ち申し上げております。 |
